本丸通信販売にて購入した品が届いたのは、お昼ご飯を食べて眠くなりながら書類仕事を進めていた、昼下がりのことだ。細長い箱に収められて届いたそれは、思っていた以上に重い。
私がよろよろとそれを両腕で抱えて、厨の入り口をくぐると、「ずいぶん重そうじゃけんど、どういたがか」と何やら冷蔵庫の扉に手をかけていた陸奥守が、くるりと目を瞠って私を出迎えた。
「ご、ごめ、」
「言てくれたらわしが持ったんに」
「う、うん」
言いながら、陸奥守はさっと私から箱を取り上げると、厨の大きな作業台の上にそれを置いた。
「開けてもえいがか?」
「うん」
段ボールのガムテープを、壁に掛かっているカッターナイフで切って開封する。中には注文した通りの、日本酒の一升瓶が収まっていた。美しい筆跡でラベルに書かれた銘柄が、土佐の名酒であることを示している。
陸奥守もそれを目に入れた途端に、ぱっと顔を明るく輝かせた。
「はー、まっことええ酒じゃのう」
「うん、ついご褒美で買っちゃった」
「ご褒美?」
「えーっと、日ごろの自分の?」
なんちゃそれ、と陸奥守が笑う。私も自分で言っておかしくなって笑ってしまった。
気が向いて、で、多少の金銭的余裕もあったので、ネットサーフィンの勢いで買ってしまったのだ。(ネットサーフィンって死語だろうか。)普段は安い第三のビールや、スーパーで買えるような日本酒、焼酎で満足している庶民の身である。
それは目の前のこの初期刀様も同じで。日常的にはうちの本丸ではお目にかかれない大吟醸の文字にときめきを隠せない様子だ。
「のう、あるじ」
「うん?」
「ご相伴に」
「もちろん」
目を見合わせてまた笑う。箱から取り出された酒瓶は、陸奥守の手によってひとまず夜まで冷蔵庫に収められた。
冷蔵庫からさつま揚げときゅうりの浅漬けを頂戴して、広い居間の隅、縁側に近い位置に陣取った。待つような間もなく、大吟醸の瓶を抱えた陸奥守が、「隠せんかったちや~」と言いながら、和泉守兼定、堀川国広、博多藤四郎を伴って現れる。
陸奥守の後ろにカルガモのようについて来た三人は「あるじ、オレたちもご相伴に」と昼間の陸奥守と全く同じような顔で言うので、私も笑ってしまいながら「いいよ」と快諾してしまった。皆、それぞれ肴を持っていて、ご相伴に預かる気満々だったのである。
そうこうしていると、部屋の別の場所にいた他の刀剣たち――日本号や大般若長光、次郎太刀やらの呑んべえ達にも当然の如く見つかり、その場はあっという間に小さな宴会と化した。
私が用意していた卓では当然足りず、寄せ集めたいくつもの卓の上では、統一感のない酒の肴と酒がごちゃごちゃと並んでいる。
件の大吟醸は皆に一杯ずつお酌をして回った。キリリとした辛口のすっきりした味わいで、香りも非常によく、どの刀剣たちも一口飲んで、ほう、と満足そうにため息を吐いた。
「なんだかあっという間に飲み会になっちゃったね」
お酌行脚を終えて、もとの自分の座布団に戻ると、いつの間にか隣の座布団を陣取っていた陸奥守が、恨めしそうに「あるじ、わしには?」と手元の空のグラスをこつこつと鳴らした。
「まだたくさんあるよ」
「かわいい子がお酌してくれにゃあ、美味しさも半減やき」
「またまた」
陸奥守は口がうまい。私が審神者になる前に勤めていた会社にもし陸奥守のような後輩がいたら、随分年上から可愛がられていただろう。すっかりうまいこと乗せられた私は、お酌をして回って少し軽くなった瓶の口を彼のグラスに傾けた。
「ええ匂いじゃのう。ほれ、あるじも」
「へ?」
「かわいい子がお酌してくれにゃあ、って言ったぜよ」
にっこり笑った陸奥守が、貸してくれと言わんばかりに手のひらをこちらに向けてくる。”かわいい子”とは陸奥守も指すらしい。全くもって異論はなかったので「じゃあ」と瓶を預けてお酌してもらった。
「いい香り」
「お目が高いのう」
自然に向けられたグラスに、自分のグラスをかちんとつけて乾杯する。一応、お酌行脚をする前に最初の一杯を飲んだのだが、二杯目のこれはもっと美味しくなったように感じられた。かわいい子のお酌パワーかもしれない。
「美味しい」
「うまいにゃあ。ええ酒じゃ」
陸奥守もゆるゆると頬を緩ませて笑っている。美味しいなと思いつつ飲み進めながらも、結構度数高めだな、と思って今更ながらラベルで度数を確認すると、思った以上の度数が記載されていた。
「わ、結構強いね」
「んー? 見してみい……ほー、おんしゃ強い酒は大丈夫やったかのう?」
「うん、ある程度は……そういえば、土佐の人はお酒強いの?」
「土佐? うーん、酒好きは多いような気もするけんど……」
随分昔に、高知県の人と飲んだことがある。その人の話では、地元じゃ酒好きばかりで、親戚の家を訪ねると昼間であってもお茶の代わりにビールが出されるのだとか。ほんとかどうかは分からない。
「陸奥守はお酒好きだよね」
「美味しいもんは好きやき」
「あんまり飲み過ぎてるところ、見たことないね」
他の刀剣たちだと、飲み過ぎて朝まで居間で転がっていたり、酔っ払って庭を徘徊し始めたり、何故だか玄関まで行って寝始めた子もいた。周りに迷惑をかけるような酔い方をする子は、少なくとも私は知らないけれど、中でも陸奥守はいつもけろっとした顔で飲んで、翌朝も何でもない顔で朝食を食べている気がする。
「ん? なんじゃあ、あるじはわしの酔うた姿が見たいちや?」
テーブルに肘をついた陸奥守が、私を下から覗き込むようにしてにやにやと笑う。別ににやにやされるようなことなんて言っていないのに、と自分の言葉を振り返ってもごもごしていると、陸奥守の頭をぺしん、と誰かがはたいた。
「あだっ」
「陸奥守、テメエあるじに絡み酒してんじゃねえぞ」
「おんしにゃ言われたくない言葉ナンバーワンじゃのう」
「ンだと?」
「もう、ちょっと、兼さん~」
陸奥守の頭をはたいたのは、隣に座っている和泉守だった。そのまま賑やかに言い争い(陸奥守は争っているつもりはないかもしれないが)を始めた二人と、それを止めようとする堀川を見ながら、そっと息を吐いて残ったお酒を飲み干す。
いつからかは分からないが、ときどき、陸奥守にじいっと見られると、何も悪いこともしていないのに後ろめたいような、息を止めてしまいたくなるような気持ちになった。なんとなく、座布団に座りなおす。
「あるじ」
いくつも並ぶ酒の肴から、枝豆を取って食べようとしたとき、いつの間にか言い争いをやめていた陸奥守がこちらに身体を傾けた。急に内緒話でもするように耳元に顔を寄せられて、私は枝豆を持つ指先すら少しも動かせなくなる。陸奥守の方を向こうと首を動かしてしまえば、鼻先が触れ合ってしまうのではないか。鼻先だったらまだいいものを。一瞬のうちにそんなことが頭の中に巡って、微動だにできない。
「酔うた姿が見たいんじゃったら、今度はわしと二人で飲ませとーせ」
場の喧騒に紛れるような声で耳に直接吹き込まれて、耳朶に触れる息に首をすくめてしまう。困ったことに、にわかに酒が回ったかのように一瞬で頬が火照ってしまった。
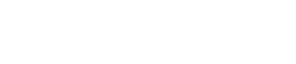
(20/07/05)
title:約30の嘘
「キーワード:土佐」 10周年記念リクエストありがとうございました!お待たせいたしました。